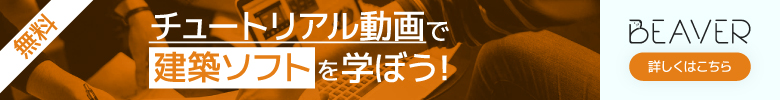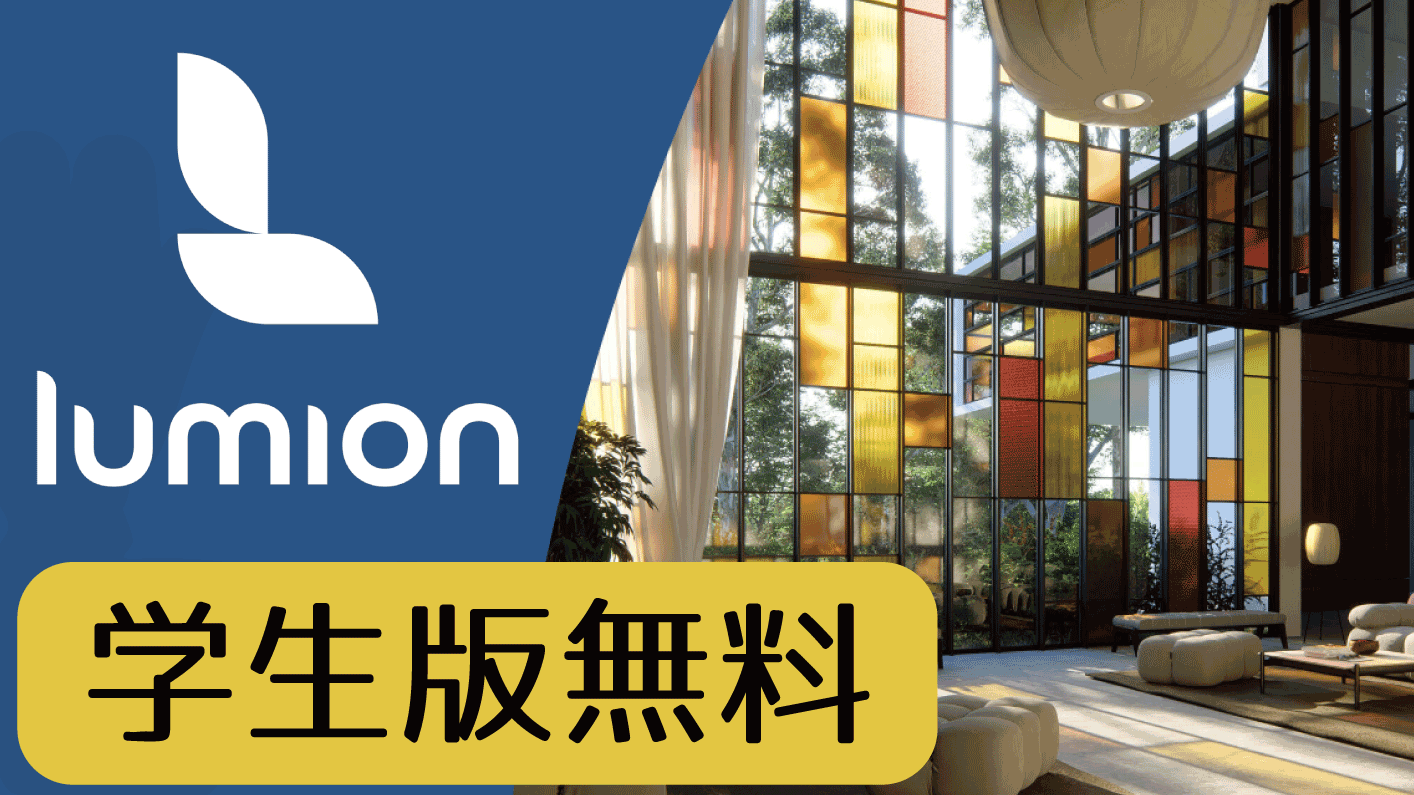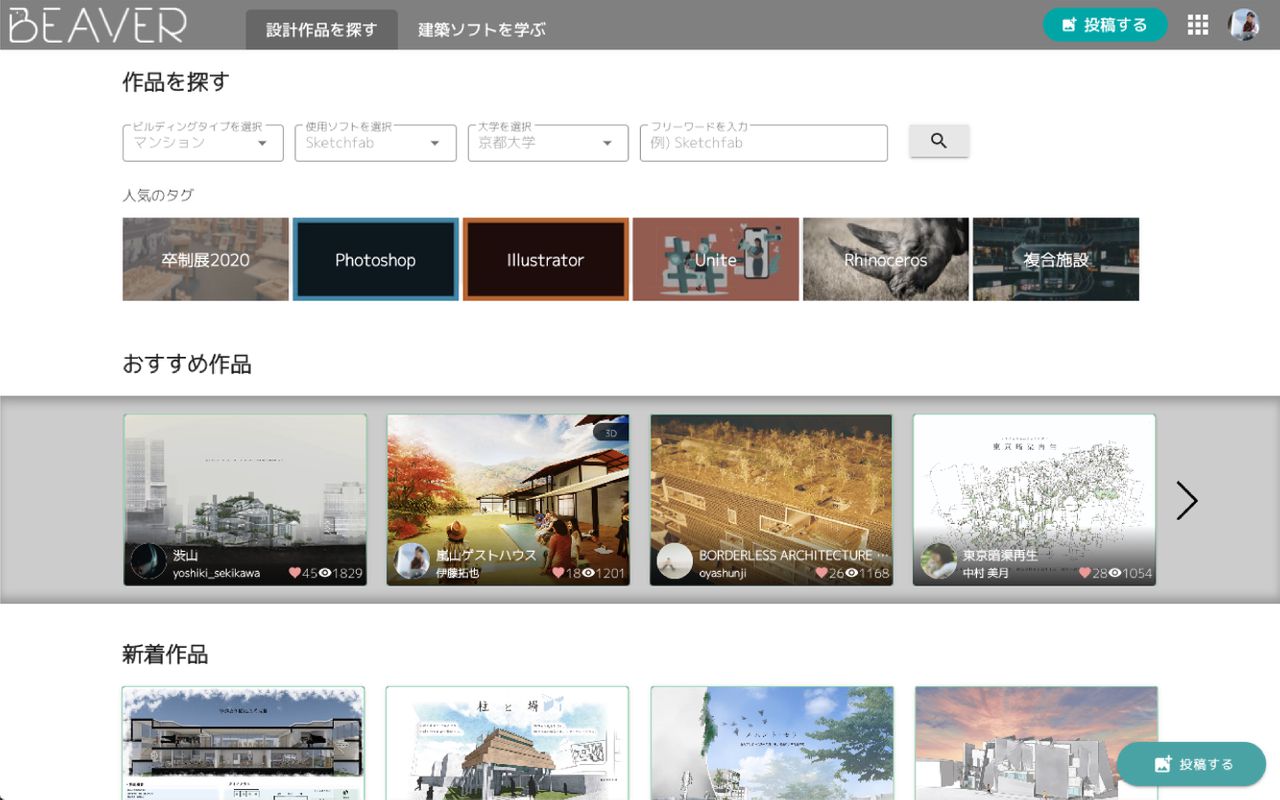【つなぎコンペ】一次審査会を覗き見!気になるコンペの裏側をレポート!

こんにちは~
そのへんにいる建築学生、あさぎ(@cryforthemoon_M)です。
今回の記事では!
先日オンラインで行われた 注目の【つなぎコンペ】の一次審査について、
その様子を一部!皆さんにお伝えしたいと思います!
コンペに出展している作品たちは、こちらからご覧いただけます。
高解像度でプレゼンボードが見られるので、ぜひ見てみてね。
建築学生の皆さんにとっては、
コンペは挑戦の場であり、大きな目標でもありますよね。
コンペではどういったところが審査員に注目されるのか?
審査会は具体的にどのような流れで進むのか?
審査員の熱い議論を追いながら 注目のポイントをまとめてみましたので、ご一読ください!
目次
[PR]
審査員とそれぞれの評価基準
今回のコンペの審査員は、『建築』や『街』、『木材』や『森』に深く関わる5名の方々です。
まずは審査員の皆さんの作品に対する評価軸について。

簡易的に組み立てられるかどうか、『つな木』の良さを生かせているかどうか。「実際にワークショップで行いたい」と感じるかどうか、という視点もありますね。着想・発想から、どのように問題解決に取り組んでいるのかを見ています

『もち』であるか、つまり森と街をどう繋いでいるのかに注目しています。それから、その「つな木」が何かの課題を解決しているか。提案に必然性があるかどうか。ニーズに寄り添えるかどうかや、純粋に生まれた空間の強さや美しさも評価したいと思っています

着想からディベロップ、プレゼンテーションの表現までの一連の流れを見ていました。発想から展開を経て、どうプレゼンまで落とし込んでいるのか、図面表現のクオリティも含めて注目しています。提案の強いメッセージ力も評価軸のひとつです

オリジナリティ、他では見ないような木の使い方をしている作品を見たいと思いました。森と街の繋がりや循環に貢献しているかどうかも大切です。提案の実現しやすさに加えて、人と人との繋がりを生んでいるかどうか、林業や製材業も含めたサプライチェーンとの連携が出来ているかどうか。まちだけで完結しない「もち」な作品を評価したいですね

はじめに直感で惹かれた作品を選び、その後なぜ自分がその作品に惹かれたのか、理由をじっくり分析することにしました。
応募作の中で自然に生まれている「評価軸」や「価値観」を探り、掘り下げていきました。
着想もそうですが、「木材ならでは」の機能を持つことや、社会性に触れていること、作ったことにきちんと意味が見いだせる作品かどうかに注目しました。コンペの枠組みを外れても強度がある提案を選びたいです。
こう見ると本当に見事に全員見ているところがバラバラで面白いですね。笑
審査員の皆さんはそれぞれ背景が異なるため、それが色濃く反映された結果、
実に多様な作品が一次審査の議論の俎上にあげられることになりました。
[求人情報]
一次審査作品 議論 「つな木」の可能性とは?
審査員の皆さんがそれぞれ推薦する作品を中心に取り上げ、
内容を掘り下げながら二次審査に進む作品を選ぶための意見交換が行われました。
二次審査に進出するのは12作品!
既に2作品は一般審査で進出が決定しているため、
審査員の「推し」作品から、残り10作品の枠に対して、21作品が議論の対象になりました。
始終活発な意見が交わされる審査会でしたが、中でも特に大きな盛り上がりを見せた部分をいくつかピックアップしました。
木ならではの「寄り添う」優しさ
今回は、つな木の「木材」という素材のあたたかみを生かして、
人の営みに寄り添うような、優しさがにじむ提案が多くみられました。
立っている樹木につな木を組み合わせる提案(SOEGI(添え木)やSOEGI Furnitureなど)は
どれも注目され、議論の対象になりましたが、
中でも子守木については、鹿という生物との関係を織り込み、
人間社会と動物社会のよりよい境界面をつくる・共存するためのアイデアとして評価されました。

(子守木は)鹿との関わりも合わせて、とてもよく考えられた提案だと思う。土壌改良法についても、よく調べられていますね。
ただ、地域が狭くて、「もち」と言えるかどうかは気になるので、そのあたりの広がりについてもう少し詳しく考えを聞いてみたいですね
他にも、「つな木」で子供のための家具をつくる、

建築の素人でも出来そうな簡便さや、出来たあとの風景が想像できるのが良いですね。ワークショップにもすぐに取り入れたいアイデア。
経年が価値に変わり、次の世代に引き継がれていく、という提案は「つな木」っぽいなぁと思います

『木育』という観点から評価出来ますね。子供にダイレクトに繋がる案だと思う。
机などの家具に対して木材を使うことは相性がいい、教室の机とかもそうだけど、使った痕跡が残るからね
特につくえつなぎは、クランプで掴んだ「傷」というネガティブな要素を
思い出が残り、愛着が湧く、というようなポジティブな価値に転換できる提案として高く評価されていました。
土木インフラを「つな木」に置き換える
提案の中には、擁壁や仮囲いなど、生活のすぐそばにある
土木的なインフラストラクチャーを「つな木」で実現する提案
(土と木で編むまちかど擁壁やHugging Wall −森・街・工事現場を繋ぎ包み込む、つな木の仮囲い−など)も見られました。

普段は気に留めないような街の風景の一部が木に変わったら、劇的に風景が変わると思います。
『柔らかな土木構造物』というか……コンクリートが当たり前になっている部分を木に置き換えて再構築出来たら、
コンクリートだらけの景観が大きく変化するのではないでしょうか

工事現場の壁は、今街の中ですごくインパクトが大きいですよね。
つな木にするとなると防音効果に不安な部分はあるけど、風景を大きく変える良さがありますね

日本は平地が少なくて微地形が多いですよね。山林にも微地形が多い。
今はそういったところにも多く擬木やコンクリートが使われていますが、生態系の中に土木が落ちていないという課題がある。
そこにこの提案のように「木」が使われたら、「生態系にあった土木」が実現できるのではないか?と思います。
技術的には検討しなくてはならないけれど、可能性は大きいし、こういうアイデアは育てたいと思いますね

仮囲いの案は僕も面白いと思いました!
ただ読み込んでいくとディティール(接合部)に疑問が出てきて……
つな木は構造体ユニットでもあるので、構造までスマートに解いてもらえたらより魅力的ですね
木の循環に建築外のインフラまで巻き込んで風景を変えていくという
「つな木」の拡張性を示唆するアイデアには、大きな可能性がありそうですね。
「つな木」のかたち、空間としての新たな可能性
純粋に「つな木」によって生まれる空間の可能性に
果敢に挑戦した木織町も話題になりました。

パースが美しいですよね!構造的に成立するなら、新しいつな木の繋ぎ方になるのではないでしょうか。
平面的な同一な形状の連続ではなく、高さによって変化する空間構成になっている。
実現したときの見え方や光、建ち現れ方が面白そうだし、これまでに見たことがないものが出来そう

たとえばイベントとして作ったら面白いと思う。材料をのびのび使ってかたちをつくっていく点は見ていて気持ちがいい。
一方で、作っておしまい、ではなく、その先の使われ方や材料の行く末まで丁寧に語って欲しい。つな木でつくる意味、というか。
こういうダイナミックなものをつくっても、つな木だからこそ解体して再利用出来る!という話があれば、さらに議論が出来ていいよね。
真正面から素直に新しい「かたち」を探求した作品に、審査員も感嘆の声をあげていました。
コンペでも、見たことがないような空間や美しいパースは、やはり見る人の心をぐっと掴みますね。
「つな木」の循環をデザインする
「もち」の範囲を超えた、新たなつな木の循環を設計する提案も議論の的になりました。
例えば、使い終わったつな木を漁礁に変える、循環の暦という作品について。

漁礁にするアイデアが良いと思いました。陸上で使い終わったあとのアイデアで、循環がデザインされているのがいいです。
漁礁が小魚を守るとしたら、組み方次第で大小サイズ展開が出来るのもいいですし、木を森からとってきて海へもどすという流れが面白いなと思いました

フナムシが木を食べるので、虫食い状態で朽ちていくことだったり、修復しづらかったり、などの問題点はあるだろうけど……
地域の木材を使って、というように、SDGsの文脈にも沿って、森に合わせた長期的なサイクルまで設計すれば、面白い提案になりそう
また、今回は「つな木」の従来のシステムに
新たなサービスを組み合わせた提案(つなぐ めぐる まわるやあとつなぎ -つな木によるもりとまちのあとつぎ-など)も見られました。

あとに繋いでいくことの大切さについて最近よく考えていて、森を守って、あとに繋いでいくために自分が今できることはなんだろう、といつも思っています。
そのためには、木材の継続的な需要をサービスで実現していく仕組みが必要ですよね。
木材は、安全性やメンテナンスが課題になりがちだけど、自然な素材を使うことで、むしろそのサイクルが噛み合って、人間の生活を 自然の生活の時間にうまく合わせていくような設計が出来たら、
そこにこそ「木」を用いる意義があるんじゃないかなと思います
他にも、サウナを「つな木」を使って実現する提案(木と、ととのう。〜木材乾燥×サウナで流通をデザインする〜など)も、
「木材の乾燥」という過程を再考するアイデアとして、審査員の心を動かしたようです。

面白そうだけど、本当に乾燥できるものなのかどうか、気になるね。笑

実際に、まちなかで建築用材を自然乾燥させて一定時間で家に使う、みたいなことやってる人がいましたね。笑
サウナならもっと早く乾燥できるかもしれないし、サウナという機能と木材乾燥がマッチすれば面白いかもしれませんね

まちなかで木材乾燥をやってしまう、という観点が面白いと思う
『都市の中で木材を乾燥させる』という視点はこれまで自分にはなかったので驚きました

BtoBの木材流通の過程にまちを介入させてくるのは、まさに「もち」ですね

『木は工業製品ではない、生き物である』、ということが伝わるかもしれませんね
「つな木」の概念をさらに拡張する
既存の「つな木」の枠組みを大きく飛び越えて、
規模という意味でも、建材の循環という意味でも、新しい視座を見せた
つな木で記す家のライフログという提案も話題に。

今の日本の住宅はほとんどが木造だけど、その「木」はほとんど隠れてしまっている。
木造なのに、木に囲まれた空間体験としては認識されていないんですよね。
住宅に使われた建材のリサイクルもあまり行われなくて、大体燃やしてしまうし……
この提案は、『使った木をリサイクルで使う』という社会的な意義が高いプロジェクトだと感じます

ヴェネチア・ビエンナーレでも行われたように、建材のデータをひとつひとつ記録して追っていくと色んな記憶や歴史が見えてくるものです。
この提案はそれをアートではなく、プリミティブなかたちで実践している。
トレーサビリティを超えた、木を大切に使うことの基本に立ち返って、これまでの「つな木」の領域や概念を超えて、拡張していく提案だと思います
綿密な調査と、独自の世界観で魅せる
中には、他にはない圧倒的な世界観を見せて、
審査員の心を魅了した作品(ねあける、森)も。

リサーチが凄くて、強く印象に残りました。異色だし、世界観がある。模型からも執念を感じますね。
提案の詳細がわからない部分もあるし、もっと話を聞いてみたいですね

今、人工林をどう天然林にもどしていくのか?という大きな実験が実際の森でも行われています。
それを観察する場をつくるというのは、もりづくりへのハードルを下げる意義もあると思います
世界観を伝えるような模型写真や密度の高いリサーチからつくられたプレゼンボードが審査員の印象に残ったようです。
「もっと話を聞きたい!」と思わせるのも提案の魅力のひとつですよね。
最後に ~二次審査へ続く!~
いかがでしたでしょうか……!!
今回抜粋したのは極々一部ですが、2時間30分にも及ぶ濃密な議論の末に選ばれた
計12作品が二次審査に進むことが決定しました!
二次審査に進出した作品は、こちらから見ることが出来ますよ~!
審査員の皆さんの「つな木」への熱意がぎゅっと詰まった、とっっっても内容の濃い一次審査でした。
応募作品はどれも力作揃いでしたが、一次審査(いつだってコンペってのは厳しいものですね)をくぐり抜けた作品たちはその中でも粒揃い。
二次審査は今回以上に白熱した審査が期待できそうですね。
本当に実現する提案もある……かも?
二次審査は10月3日に行われます。そちらの結果もぜひ、チェックしてみてね!!